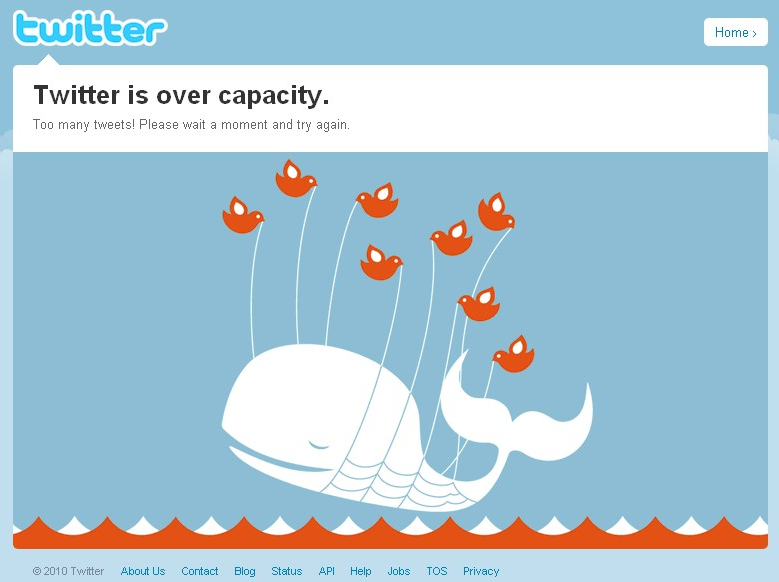ネット選挙解禁に向けて政治家先生が注意するべき3つのポイント
Facebookを選挙に活用する上での注意点とは〜政治家のソーシャルメディア活用
先日来、夏の参議院選挙に向けて、いよいよでネットを活用した選挙活動が解禁される見通しとなってきていますね。
>>なりすまし対策で罰則強化、ネット選挙解禁で自公最終案判明 3月上旬成立へ
昨年末の衆議院議員選挙の際、「事実上ソーシャルメディアなどネットを活用した選挙は解禁されている?」という記事を書きましたが、これで堂々とFacebookやツイッターを使って票集めができるようになりそうな気配です。
しかしおそらく、ネット選挙解禁という大きな流れの中で、喜んでいる代議士先生と、困惑している政治家先生、大きくふたつにわかれているのではないかと想像できます。
前述のように「よっしゃ!これで堂々とFacebookが使えるぞ!」とお喜びの先生。
一方、「ネット選挙解禁と言われても何がなんやら。。でもみんなFacebookやらツイッターやら始めるだろうから、自分だけやらないわけにはいかないなぁ。。う〜ん。。。」とお困りの先生。。
というわけで、今回は後者の先生方に、ソーシャルメディアを始める上での注意点を、僭越ながらお伝えさせて頂きます。
企業のFacebookページや経営者のFacebookページアカウントの運営をお手伝いさせて頂いている中から、政治家先生にもぜひ知っておいて頂きたいポイントを3つまとめてみました。
・とにかく早く始めましょう
次の参議院選挙は7月末。ということは逆算すると、6月ぐらいにFacebookを始めたらいいか。。と、呑気に構えていらっしゃるそちらの先生。ソーシャルメディアの中にいる住民はバカではありません。
明らかに選挙のために始めたアカウントなど、すぐに見破られ逆効果となります。「どうせ選挙が終わったらもう投稿しないんだろ」としか思われません。
一刻も早くFacebookやツイッターを始めて、ソーシャルメディアの住民とコミュニケーションをとることを始めてください。
・主義主張をつらつらと書くものではありません

私が当選した暁には。。現政権はこうだからダメなのだ。。などなど、先生の主義主張ばかりを書き込んでも、ソーシャルメディアではウケません。そんなものはホームページやブログでやってください。たまにならいいですけど。。
・普段、一般庶民が見られないところを見せましょう

先生でないと踏み入れることのできない建物や、体験できないことを見せ、我々のような一般の人間が擬似体験できるような内容のものを、できれば画像付きで投稿してください。
もちろんセキュリティ上の問題で見せられないものも多々あることは重々承知しています。
ただ、あらゆる場面、場所で先生の周りを見渡してみてください。意外と「これ、今の自分にとっては普通だけど、議員じゃない時には考えられなかったなぁ。。」というモノ・コトがあるはずです。僕たちが興味を持つのはそういうものです。
細かく言い出すともっともっとお伝えしておきたいことはあるのですが、最初はこの3つのポイントに気をつけてください。とりあえず失敗することはありません。成功するかはまた別のハナシではありますが。
ここまで読んで「こんなことして票に繋がるのかよ」とお考えの先生。逆にお聞きします。
選挙の前にやたらといろんなところにお顔を出して多くの庶民と握手をするのはなぜですか?
選挙カーでお名前を連呼するのはなぜですか?
ポスターのお名前表記を、わざわざ読みやすくするためにひらがなで書くのはなぜですか??
まずは名前と顔を覚えてもらい、接触することによって親近感を持ってもらうための動きだと、僕は思っているのですが、違いますでしょうか?
それ、選挙期間が始まる前から、ソーシャルメディアでできます。
2年、3年と有権者とソーシャルメディアで交流を続けている先生と、方や選挙が始まるからと急ごしらえでソーシャルメディアを始めた先生がいらっしゃったとします。
今や日本では5000万人を超えると言われるソーシャルメディアの住人たちは、どちらを応援するでしょうか??
田村でした。
【関連記事】
安倍総理のソーシャルメディア活用に見る政治家の効果的な情報発信とは
管理人実績・著書・セミナー・プロフィール